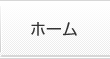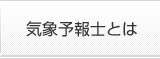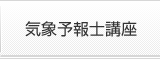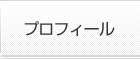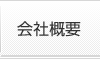「数値予報ができないこと」ちょこっと…てんコロ.アドバイス更新しました
ちょこっと…てんコロ.アドバイス16 学科・専門:数値予報ができないこと
昨日、私はこんなシンポジウムを聞きに行きました。「京」コンピューターが、今後の気象予測にどんな感じで貢献してくれる
のか?そんな話が聞きたくて参加してきました。とてもワクワクするお話でした。ただ、ちょっと持ち時間が少ないみたいで
もっと詳しい話が聞きたかったな…という結果でした。また、関連講演があれば聞いてきたいと思います(^_^)/
これと、関係あるんだかないんだか…ふと数値予報の限界について思いついたので、今日はそのお話です。
数値予報は、現代のお天気予報になくてはならない基盤のような存在です。だからと言って、なんでもかんでも予想できる
わけではありません。数値予報結果を扱う気象予報士さんは、そのことを分かった上でデータを扱わなければなりません。
ですから、気象予報士試験でも、数値予報の限界について頻繁に出題されるわけです。
①格子間隔と表現可能気象現象のスケール
数値予報で表現できる現象は、モデルの格子間隔に依存しています。具体的には、数値予報モデルで表現できる
気象現象は、水平格子間隔の5~8倍以上の水平スケールを持つ現象です。だから、例えばGSM(全球モデル)は、
水平格子間隔が20kmですから、現象の水平スケールは100km以上ないと上手に表現できないということです。
だから、地上天気図に登場する規模の移動性高気圧とか温帯低気圧などは、非常に精度良く表現できますが、夕立など
水平スケールが10km程度の個々の積乱雲を表現することはできないということです。
⇒できないことへの対応
モデルの格子間隔より小さいスケールの現象だからといって、例えば上記のような積雲対流が格子点の物理量に与える
影響は大きく、シカトするわけにはいきません。これらの現象(サブグリッドスケール現象)による効果を格子点値に反映
させることを「パラメタリゼーション」と言います。
②格子間隔の限界
①の問題を解決するために、「じゃあ格子点間隔を小さくすればいいじゃん!」と単純に思いますが、そう簡単には
いきません。確かに、格子点間隔を小さくすれば、より細かい現象を予測することができますが、それと同時に計算量が
膨大になり、計算時間が増加します。しかも、より正確な初期値が求められるため、今の段階では技術的に不可能です。
③予報時間の限界
数値予報モデルを用いた力学的手法による予報期間の限界は、10日~2週間程度です。これは、総観規模の低気圧や
高気圧の時間スケールに相当します。小さいスケールの現象ほど、有効性が切れるのが早い傾向にあります。また、
予想時間が長くなるとともに、予報誤差が育ってしまいます。特に初期値に含まれる誤差は、観測値の誤差をはじめ、
客観解析や初期値化の過程で必ず発生し、これを完全に排除するのは不可能です。
⇒できないことへの対応
初期値に必ず誤差が含まれることを逆手にとって、敢えて複数の初期値を用意してそれぞれ数値予報を行うという方法が
アンサンブル予報です。予報の有効期間を延長する手法として、週間予報や長期予報で用いられています。
④地形の平滑化からくる限界
数値予報モデルの解像度が上がっても、やはりモデルに組み込まれる地形は現実のものとは違い平滑化されています。
複雑な山岳や盆地などは特に十分表現できないのですが、地形は下面境界条件となりますから、地形が原因となる
擾乱や、モデルと実際の地形の高度差からくる地上気温などの要素に誤差が生じます。
**** **** **** **** **** **** ****
このように、数値予報には様々な限界があり、それを補う別の方法が取られているものもあれば、その誤差を踏まえて
気象予報士が取り扱いに注意しなければならない数値予報結果も多くあるわけです。
専門分野の試験を受ける方は、この辺りのことをまとめておきましょう(^_^)/
この他にも、ユーザー登録していただくと無料で見られるミニ講座をアップしていきたいと思います(^_^)/
てんコロ.のeラーニング気象予報士講座は、学科一般分野(法令をのぞく)・学科専門分野・実技講座があります。
それぞれ、単元ごとに購入可能です。
◆一人で勉強してても分からない所がある方
◆得意な単元と不得意な単元がある方
◆遠くてスクールに通えない方
ぜひ、てんコロ.のeラーニング気象予報士講座をのぞき見してみてください(^_^)。
てんコロ.が一体ぜんたい、どんな先生なのか…?不安だな~という方は、以下の無料コンテンツをご覧ください!
*ユーザー登録していただくと、以下のコンテンツが無料でご覧になれます*
☆オリエンテーション(気象予報士試験の勉強をはじめようかな~という方へ)
☆実技講座学習ガイド(実技試験の勉強を始める方へ)
☆第38回気象予報士試験 学科試験(一般・専門)解説
2012年12月13日
カテゴリー:てんコロ.のワンポイント, 講師より